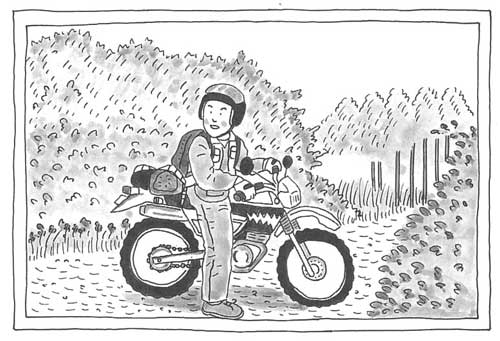 |
Hanzubon #22
「天に通じた道」
|
まさしく、文明さまさまである。 先日、奥さんに冷蔵庫を買わされたのだが、こいつがすごい。冷蔵庫のくせに遠赤外線なる不思議な光線を放ち、かつ、解凍してしまう部屋を持っているのだ。凍らせておいて溶かす。この相反する行為を、たった1台でやってのけてしまうベンリな代物なのだ。 洗濯機もズボッと洗濯物を投げ込めば、水量を見分けてしまい出来上がれば“ピッピッピッ”と知らせてくれる。 もちろん、お風呂だってマイコン制御。あっちでピッピ、こっちでチンチン・・・。まさしく最近の奥さまは楽チンチンなのだ。
三重県と滋賀県の県境にある鈴鹿山脈の奥深くに、茨川という集落跡がある。 茨川といっても、川の名前ではない。廃村になった村の名前である。この廃村に、オートバイで出かけてみることになった。 僕の場合、異常なまでの怖がりであり、廃村などと聞いただけで、なにやらオドロオドロした恐怖が背筋を走ってくる。その昔、浅草の花やしきで、おふくろに 「あんたとは、もう2度と遊園地には行かないヨ!」と言わしめるほど、お化け屋敷の中で泣き狂った男である。 オートバイの取材であるからして、別にこれといった装備もなく、オフロードバイクに寝袋と食料だけ積み込んで、僕は募る恐怖感を抑えつつ東京を出発した。 今回のツーリングには、以前茨川に住んでいらっしゃった筒井みつ江さんという方が廃村内を案内してくれることになっている。 桑名インターから、さらに走ること1時間半。筒井さんとの待ち合わせ場所である茨川林道の入口に着いた。 この林道の終着点に茨川廃村はある。茨川の廃村後、いつしかこの林道も役目を失い廃道になっていて、どこまで進めるかが問題である。筒井さんを取材車に乗せて、僕らは林道を奥へと進み始めた。 林道は、愛知川の支流茶屋川に沿って、さらに奥地へと続いている。 やがて、林道は狭い谷筋に入り、谷底を這うようにオートバイで走っていると、両側のそそり立つ山面に、思わず押し潰されそうな圧迫感を感じてしまう。 すでに人の往来が途絶えてしまった林道はひどく荒れていて、土砂に埋もれていたり、川に所々が押し流されてしまっている。 何とか走り続けていたが、とうとうどうやっても越すことの出来ない大きな崩落跡に出くわしてしまった。道の上に10メーターほどの土砂が積み上がっている。茨川までまだ5キロほどの距離を残していたが、仕方なく取材車とオートバイをそこに停めて、荷物を背負い、僕らは茨川へと歩き始めた。 筒井さんはさすがに元・山里の人である。ご高齢にもかかわらず、あっという間に息の上がった僕らをよそに、ヒョイヒョイと崩れた林道を進んで行く。 「昔は、この川で尺を超えるイワナが何匹も釣れたんですけどね・・・」 茶屋川をのぞくと、淵には土砂がたまり、全体的にうすっぺらい川になっている。 他の川でもそうであるように、林道を通すにあたって、アホな業者が削った土砂をおそらく川に捨てたのだろう。辺境の地にしか住まないイワナは、すでにこの川にはいないようだ。
さらに歩くこと1時間。やっとの事で集落跡の入口にたどり着いた。 両側の谷すじには木が茂り、急勾配の山面が狭い谷間をさらに窮屈な感じにさせていて、とてもここで人が住んでいたとは想像しづらい。集落は、ここから上流約500メートルの間に茶屋川を挟むように広がっていたらしい。 筒井さんの住んでいた昭和30年代には、家屋が川に沿って10戸ばかり点在していて、50人ほどの人々が暮らしていたそうだ。 筒井さんと廃村に入ってみる。 直径1メーターほどある大きな釜の転がる河原を越えると、村の分教所があった。現在は、滋賀県の高校の山岳部が山小屋として使っているようだ。 さらに村の中へと続く道を進む。肩口まで伸びた夏草の合間から。その上に家が建っていたのであろう石垣がところどころに見つかる。 筒井みつ江さん宅跡にも寄ってみた。母屋はその土台すら見られず、土間のあったあたりに大きな鍋が落ちているだけで、ここに家が建っていたことを想像できるものは、ほかに何ひとつ見つからなかった。 さらに進む。道は途中一度河原に出ていて、向こう側に渡る橋がここにかかっていたらしいのだが、その跡は何も見当たらない。 川を渡ることを諦めて、そのまま200メーターほど進み、小さな杉林を抜けた。そこには潰れてはいるものの、小高い丘に母屋ごとそのままの状態で残った廃屋に出会った。村から少し離れていることもあって、焚き火の薪にされずに済んだのであろう。 廃屋の周りには、いろいろな日用品が散乱していた。木製の冷蔵庫、潰れた椅子。それに文字も針も取れてしまっている時計・・・。人だけが忽然と消え去った、そんな感じのする廃屋だった。 潰れた母屋の少し離れたところに、ほぼ完全なままで小屋が建っている。中を覗くと風呂小屋で五右衛門風呂だった。釜を見て右側の壁には小さな棚と流しが付いていて、その棚の上には歯ブラシやカミサリが、先住者が使っていたままの状態で置き去りにされていた。 錆びたカミソリを手に取ってみる。置かれた棚には、赤茶けた錆の色がカミソリの形で残った。使い込まれた歯ブラシは、毛先がクルクルと巻き上がっている。それらは、この地で暮らした人々の生活の匂いを色濃く残し品々だった。 人が1人やっと入れる程度の風呂釜に入ってみると、割れた窓ガラスの向こうに、夕陽に染まった鈴鹿の山々がうっすらと見えてきた。 |
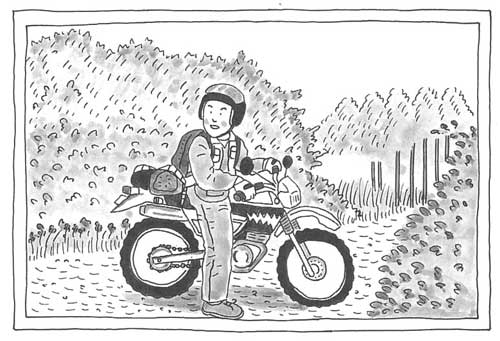 |
イラスト:Yoshida.ken
|
茨川はまさしく鈴鹿山脈最奥、辺境の地である。七重八重に周囲を山で囲まれ、背後には標高1165メーターの高峰、藤原岳が村を見下ろすようにそびえ立っている。 茨川の歴史は意外と古い。今から1100年ほど前の弘仁元年の頃に近くで銀山が見つかり、その鉱山の働き手のために4、5軒の茶屋が出来た事が始まりとされている。閉山後は木材中心の生活が昭和38年8月7日の廃村に至るまでの主な産業となっていた。 茨川には、筒井姓を名乗る方が多い。 これは、織田信長の知遇を得た戦国武将、筒井順慶が関ヶ原の合戦の後、勝った側であったにもかかわらず、日和見主義者などと呼ばれ、世を忍ぶように地族を引き連れ、君ヶ畑奥深い山々を越えて、この茨川に身を隠したためだそうだ。 重なる取材に嫌な顔ひとつ浮かべず協力していただいた筒井みつ江さんは、その順慶の14代目に当たる方で、昭和30年までこの茨川に住んでいらっしゃった。 茨川と最も近い村は、その藤原岳を越えた三重県側の員弁郡は北勢町である。 この北勢町と茨川を結んでいるのが治田岬であり、茨川の人々は木炭を背負って、この険しく長い峠道を越え、その炭を売ったわずかなお金で米や日用品を買い、ふたたび峠を越えて帰って来た。茨川の人々にとってこの険しい峠道が、いわば生活道路だったのだ。現に、離村していった茨川の人々は、そのほとんどが三重側に移り住んだ。 茨川は、時代の流れから隔離されたように、ひっそりと小さな谷間にたたずんでいた。 昭和29年。そんな茨川に、村の真ん中を流れる茶屋川沿いに、下流の大きな町とつながる“茨川林道”が全面開通した。それは、村人たちのかねてからの願いでもあった。 全長12キロメートル、幅3.6メートル、谷の山肌を削り何十という橋を谷にかける難工事であった。 しかし、たった10戸も満たない小さな集落に、投資効率ばかり優先する行政が道を通すわけがない。 狙いは、茨川の山林資源にあつた。茨川の人々の想いとは別に、日本は戦後の復興期に入り、猛烈な資源消費の時代を迎えていたのだ。が、狙いはどうであれ、茨川の人々は開通を歓迎した。険しい歩き道の苦行から解放されたのだから・・・。 全面開通とともに下流の町からやって来たのは、大型のトラックとチェーンソーだった。 まずチェーンソーによって、ノコギリやオノによる木こり仕事がなくなった。それに原木を木炭にするまで1ヶ月もかかり、とても次から次へと来るトラックの荷台を埋めることは出来なくなり、原木は炭焼きされずに原木のまま積み出されるようになった。 1俵1俵、背中に担いで峠を越えていた頃の能率とはケタ違いに伸び、連日やってくるトラックには原木のままの木材が次々と積み込まれて行った。 業者は業者で、断崖に無理につけた林道がすぐに荒れることを知っていたから、なおさら大急ぎで買いつけて行く。茨川は集落始まって以来の好景気を迎えていた。 しかし、気がつくと木は切りつくされ、たった5年の間に鈴鹿の山々は裸になっていた。それまでの手仕事でゆっくりやれば、いつまででも人間の生活を支えられたはずの山が、たった5年で裸になってしまったのだ。 山に目ぼしい物がなくなると町からトラックも来なくなり、いつの間にか林道もあっという間に荒廃して、茨川はその昔の辺境の地に逆戻りしてしまっていた。それまでは現金なしで暮らせた山の生活が、何を決めるにも金が必要になってしまった。 やがて生業の道を絶たれた村は、1戸減り2戸減りで、昭和38年の8月7日に最後の住人の離村とともに茨川は廃村となる。千年以上続いた茨川の歴史は、たった数年の林道の歴史に脆くも葬り去られてしまったのだ。 ・・・あれから27年。茨川は静かな森に帰りつつあった。 村を飲み込んだ美しい山や森、茨川の自然に離れてみて、僕はあらためて自然のその神秘的なでっかさを感じさせられた。
僕が廃村の茨川を訪れたのは、これで2回目ということになる。 前回はテレビの取材だった。11月下旬の肌寒い頃である。その時と比べて茨川は、すっかり夏草に被われてしまっていて、季節の移り変わりがこんなに景色を変えてしまうのかと驚いてしまう。 僕たちが住んでいる街ではこんなに変わらない。 夜、分教所の前で焚き火を囲んだ。背中の後ろに広がった真っ暗闇に少々ビビリながら、筒井さんにとって“ふる里”とはどんな想いを抱くものなのか、興味本位な気持ちで訊ねてみた。 筒井さんは言う。 「私にとって、生活している所がふる里であって、茨川がふる里である気はあまりしない」 僕ら、コンクリートに囲まれた空調によって生み出された快適さを、いみじくも心地良く迎え入れてしまっている人間にとっては、不可解なお答えである。 こんな素晴らしい環境をなぜ捨ててしまったのだろう。 「あれ以上、あそこに住んでいくのと無駄でした」 ・・・僕たちの都会ボケは、かなり重症である。こういった辺境の地で生活をしていた人たちの、心の痛みや淋しさを何ひとつ理解せずに、ノコノコ馬鹿づら下げてやって来てしまっている。僕らは今回のツーリングを経て、とても自分たちの生き方が思いやりに欠けた淋しい生き方のような気がした。 林道ツーリング・・・。その面白さはよく分かる。自然が豊富に残された山の中を走るのは、大変気分のよいものである。 ただ、僕らが走り回る林道の中に、こんな歴史を持った林道があったことを、僕は忘れずにおきたいと思った。 “ピッピッ転倒しまス!” マイコンオートバイがこんなことまで言い出したら、僕はもうオートバイに乗ってあげないつもりだ。 |
 |
||||