 |
 |
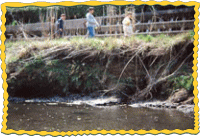 |
 |
Tanken #01
|
カワセミは、多摩川野鳥界のスター的存在だ。 エメラルドグリーンに輝く翼や、コバルトブルーの背中にオレンジ色の胸──。“水辺の宝石”と呼ばれるほどの美しい鳥なのだ。 体長は7センチくらいで、空中から水中へダイビングして小魚を捕まえて生活している。 カワセミというと、渓谷の清流に暮らす鳥というイメージがあるけど、じつはそうじゃない。昔、まだ身近なところにも自然がいっぱいだった頃には、川の中流や下流それに池や沼にも、ごく普通に人の近くでも暮らしていた鳥だったんだ。 でも時代が変わって、水質が悪くなって、エサの小魚が減ってしまったり、川岸のコンクリート護岸が増えたりして、だんだんと街に近い平野部からは消えていってしまった。そして、いつの間にか山あいの清流でしか見ることの出来ない貴重な鳥になってしまったんだ。 |
東京世田谷のカワセミの巣。巣穴の上を散歩の人たちがしょっちゅう歩いてる。 すごいなぁー・・・ 。
|
そんな「幻の青い鳥」とまで言われた鳥が、川崎や世田谷の水辺に帰って来たのは、なぜなんだろう。 カワセミは意外なところに巣を作る。水際にある切り立った土の崖の中腹に、細い穴を掘って、その中で卵を産みヒナを育てるんだ。なるほど、崖の中腹ならば、ヘビやネズミなど地上の外敵からヒナを守れそうだ。 家の近くでも、今年も巣穴は3ヶ所も見つけることができた。何故3ヶ所なのかというと、巣穴を掘れる土の崖が3ヶ所あるからだ。このあたりの多摩川は、川も大きく流れが複雑で、増水のたびに大きな中州が削られ、巣づくりに具合のいい土の崖ができるんだ。 街中なのに何故そんなに増えたのか、考えられるその原因を書くと、 ① 水質や水辺のガサガサが再生されて小魚が増えた。 ② 護岸工事や土手の改修工事も、自然工法が用いられ巣作りの場所が増えた。 ③ チャレンジャーのカワセミが出現した。 ①や②は最近の自然や環境への関心の高まりから言えば、簡単に想像できる。でも③は、僕も初めて知ったことで、見た時はすごく驚いた。 世田谷の野川にいたカワセミは、川の近くのペットショップの水槽から、売り物の小魚を横取りしては、エサの少ない時期を乗り切るそうだ。ちょくちょく、その店の前に飾られた水槽の上で、金魚をねらうカワセミが目撃されているんだから面白いよね。 土の崖のない川崎市を流れる支流では、コンクリート護岸の中ほどに開けてある、水抜き用の塩ビ管を使って、ヒナを孵すんだからスゴイッ!まったくどれもチャレンジャーな生活を成功させているようで感心させられてしまうのだ。 |
 |
 |
|
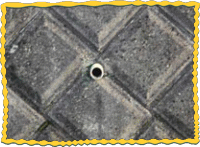 |
||
|
そんな平野部のカワセミが、昔のように数を安定させてきているのに、まだ自然がいっぱい残っているはずの上流域や地方の水辺では、今、カワセミの減少が進んでいて、心配されてるそうだ。 甦ってきた平野部のカワセミと、消えつつある上流部のカワセミ・・・。その消えつつある原因が、昔、平野部で少なくなった原因とまるで同じ・・・というのがあまり笑えないね。 |
中本 賢
 |
||||